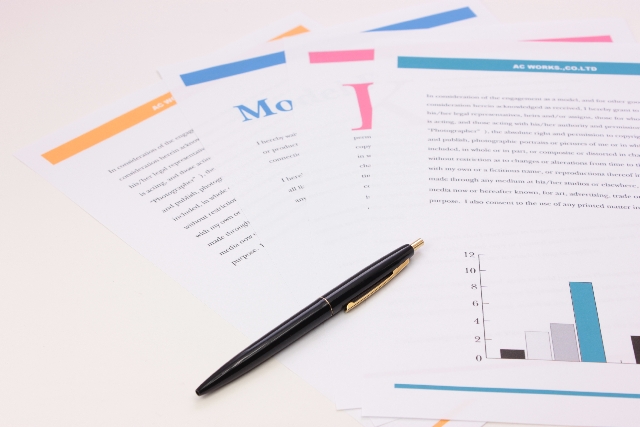


住民税についての質問です。
去年一年失業保険と、運悪く大怪我をして入院、自宅療養していた友人についてです。
就業時は給与は月に20万~25万円で税金も引かれてたので住民税は支払われてたと思ってたそうです。
先月ようやく職場復帰したら「住民税四年分、120万円、差押えで口座引き落とし」と区役所から連絡が来たそうです。
入院費や生活費を親や友人から100万円程借金していて、家賃もあるので、大変困惑しています。
生活保護や自己破産、もしくは延期や免除などないのでしょうか?
去年一年失業保険と、運悪く大怪我をして入院、自宅療養していた友人についてです。
就業時は給与は月に20万~25万円で税金も引かれてたので住民税は支払われてたと思ってたそうです。
先月ようやく職場復帰したら「住民税四年分、120万円、差押えで口座引き落とし」と区役所から連絡が来たそうです。
入院費や生活費を親や友人から100万円程借金していて、家賃もあるので、大変困惑しています。
生活保護や自己破産、もしくは延期や免除などないのでしょうか?
あまりにもいい加減な投稿があるので意見します。
民間-民間のお金の貸借は自己破産によって免責をうければ、
返済の義務はなくなります。
但し、租税・公課は免除されません。
国・地方自治体-民間のお金(租税・公課)は生活保護許可
を受ければ支払い・返済の義務はなくなります。
生活保護法(公課禁止)第57条 被保護者は、保護金品を
標準として租税その他の公課を課せられることがない。
とあります。
租税とは税金のことで公課とは国または地方公共団体によって
課せられる租税以外の公の金銭負担。分担金・手数料・使用料
などをさしています。
つまり、たとえ租税及び公課の滞納金があっても生活保護許可を
得た者に対して税金及び国民健康保険料を課してはいけないこと
になっています。
民間-民間のお金の貸借は自己破産によって免責をうければ、
返済の義務はなくなります。
但し、租税・公課は免除されません。
国・地方自治体-民間のお金(租税・公課)は生活保護許可
を受ければ支払い・返済の義務はなくなります。
生活保護法(公課禁止)第57条 被保護者は、保護金品を
標準として租税その他の公課を課せられることがない。
とあります。
租税とは税金のことで公課とは国または地方公共団体によって
課せられる租税以外の公の金銭負担。分担金・手数料・使用料
などをさしています。
つまり、たとえ租税及び公課の滞納金があっても生活保護許可を
得た者に対して税金及び国民健康保険料を課してはいけないこと
になっています。
雇用形態について
今月、同じ職場の男性社員と結婚しました。
私も正社員として働いております。
結婚を機に、正社員からパート契約になるよう打診がありました。
この場合、
①会社都合退職として退社すればすぐに失業保険は降りますか?
②辞めずにパート契約した場合、社会保険に加入しない(?)と言われています。
今後、産休や育児休暇(育児手当?)などが総収入額の50%になるためどう考えても
正社員で働いた方が良いと思うのですが、旦那の扶養に入って扶養手当を貰い、
住民税など免除されるよう108万円以下で働いた方がお得でしょうか?
現状は、手取り17万円・賞与はありません。
③住宅ローン審査が通り、本審査手前の状態ですが、
登記権利を、旦那10:私0にした方が住宅ローン減税はたくさん貰えますか?
今後も共働きを続ければ5:5でも2人分貰えると説明を受けました。
しかし、子供が出来れば私が仕事を辞めますし、
上記のようにパート契約になることもあり悩んでおります。
色々調べてみましたが、理解するのが難しく…。
お手数ではありますが回答いただければと思います。
長文申し訳ございません。宜しくお願い致します。
今月、同じ職場の男性社員と結婚しました。
私も正社員として働いております。
結婚を機に、正社員からパート契約になるよう打診がありました。
この場合、
①会社都合退職として退社すればすぐに失業保険は降りますか?
②辞めずにパート契約した場合、社会保険に加入しない(?)と言われています。
今後、産休や育児休暇(育児手当?)などが総収入額の50%になるためどう考えても
正社員で働いた方が良いと思うのですが、旦那の扶養に入って扶養手当を貰い、
住民税など免除されるよう108万円以下で働いた方がお得でしょうか?
現状は、手取り17万円・賞与はありません。
③住宅ローン審査が通り、本審査手前の状態ですが、
登記権利を、旦那10:私0にした方が住宅ローン減税はたくさん貰えますか?
今後も共働きを続ければ5:5でも2人分貰えると説明を受けました。
しかし、子供が出来れば私が仕事を辞めますし、
上記のようにパート契約になることもあり悩んでおります。
色々調べてみましたが、理解するのが難しく…。
お手数ではありますが回答いただければと思います。
長文申し訳ございません。宜しくお願い致します。
1.ケースバイケースです。解雇できないことがほとんどです。
3.はい。
ただし、売却時に3000万控除が2人分使えなくなります。
3.はい。
ただし、売却時に3000万控除が2人分使えなくなります。
確定申告についてなんですが…私は現在主人の扶養に入っています。昨年10月に退職し、翌月から失業保険を貰いました。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
質問者さんの場合、年内に退職されたということで、おそらく年末調整を
受けてないものと予想されます。
退職した後、会社から「平成19年分給与所得の源泉徴収票」いうのを
もらったのではないかと思います。
その書類の一番右側の源泉徴収税額欄に金額の記載があれば、確定申告
をするとその金額のいくらかが戻ってくるはずですよ。
お友達が、「市役所で所得証明書を取って・・・」と言っているのはこのことでは
ないでしょうか?
必要な書類は等は、
・平成19年分給与所得の源泉徴収票
・生命保険、地震保険料控除証明書、(本人の契約分があれば)
・国民健康保険、に加入していたならその支払った金額
・国民年金に 〃
・印鑑
・還付金を受取る銀行口座№など
私が考えられるのはこれくらいかなと思います(^-^)
受けてないものと予想されます。
退職した後、会社から「平成19年分給与所得の源泉徴収票」いうのを
もらったのではないかと思います。
その書類の一番右側の源泉徴収税額欄に金額の記載があれば、確定申告
をするとその金額のいくらかが戻ってくるはずですよ。
お友達が、「市役所で所得証明書を取って・・・」と言っているのはこのことでは
ないでしょうか?
必要な書類は等は、
・平成19年分給与所得の源泉徴収票
・生命保険、地震保険料控除証明書、(本人の契約分があれば)
・国民健康保険、に加入していたならその支払った金額
・国民年金に 〃
・印鑑
・還付金を受取る銀行口座№など
私が考えられるのはこれくらいかなと思います(^-^)
詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
会社を辞めて、失業保険を貰うのと、パートをするのと、どちらがトータル的に収入が多いですか?ちなみに関東の主婦の場合です。
あくまで一般的に言えばという前提なら、失業手当をもらう方が多いはずです。
ただし、個々の状況によって違いますので、あなたに当てはまるとは限りません。
退職理由、給付日額、扶養について、国保の場合の保険料、ご主人の課税所得などなどで違ってきます。
ただし、個々の状況によって違いますので、あなたに当てはまるとは限りません。
退職理由、給付日額、扶養について、国保の場合の保険料、ご主人の課税所得などなどで違ってきます。
関連する情報